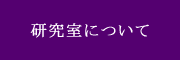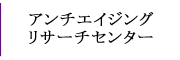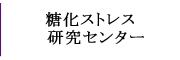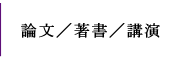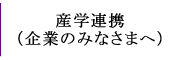糖 化
老化の危険因子には免疫力、酸化ストレス、身体ストレス、生活習慣、代謝解毒が知られています。また老化度を判定する項目としては、相対的機能年齢評価である筋年齢、血管年齢、神経年齢、ホルモン年齢、骨年齢があり、これらをバランス良く調和させることが健康長寿に繋がると考えております。
平成18年度国民健康・栄養調査によると糖尿病とその予備群は1840万人に達するという結果でありました。この数は前回調査から4年間で250万人の増加であり、今後もさらに増加すると予測されています。
糖尿病合併症の病態は加齢に伴って現れるさまざまな老化現象と良く似ていることから、糖代謝異常と老化進展との関連性が報告されています。また、ブドウ糖(グルコース)は生体において重要なエネルギー源であるため、生命を維持する上で不可欠な物質です。このため生体へのグルコースの影響は糖尿病の有無にかかわらず全ての人に老化の危険因子として関与する可能性があります。しかし、グルコースおよび糖代謝異常の老化への影響は解明されておりません。
タンパク質はグルコースと共存することにより非酵素的に反応し、不可逆的な変性を起こすことが知られています。この反応は糖化反応と呼ばれ、タンパク質とグルコースが結合し、アマドリ化合物を経て糖化最終生成物(AGEs)を生成します。AGEsにはその生成中間体である3DG(3-デオキシグルコソン)をはじめ、ピラリン、ペントシジン、CML(カルボキシメチルリジン)など、数100種類の物質が同定されています。また最近になってCMA(カルボキシメチルアルギニン)が、コラーゲン中に特異的に生成するAGEsであることが確認されています。これらAGEsの生体内蓄積には下記疾患への影響があげられます。
- 糖尿病性網膜症
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性神経障害
- 動脈硬化症
- 骨粗鬆症
- アルツハイマー病
- 神経変性疾患
- 癌
- 皮膚硬化
さらに、糖化反応およびAGEsの生成・蓄積はタンパク質の褐変化や分子間の架橋結合を伴うため、肌のくすみを起こし、ハリや弾力性の低下を招きます。このため美容的観点からもマイナス要因となっています。しかし、これまで糖化反応の影響やAGEs蓄積の影響を老化や加齢の観点から研究された例は少ないといえます。
そこで本研究室では、生体中に生成・蓄積する各種AGEsの測定を行うと共に、加齢に伴う生成・蓄積量を調査していきます。さらに従来用いられている老化判定項目やAGEs蓄積に関与するさまざまな疾患の進行レベルとの関係を比較することによって、生体内AGEs量の測定が老化度の判定に応用可能かを解析していきます。
また、これまで行ってきた食品、サプリメント、化粧品、健康器具類の臨床的評価ついても生体内AGEs量の測定を積極的に行い、その抗糖化作用についての検証をしていくつもりです。
本研究室では採血による各種AGEsの測定はもちろん、 、蛍光分光方式で、皮膚・皮下の血管壁に蓄積されるA G E sをAutoflourescence(AF)として検出し、その積分データをAGEs値として算出する非浸襲式AGEs計測システムであるAGE Reader TM( DiagnOptics B.V.社製)を導入し、データの集積を加速させることを可能にしました。
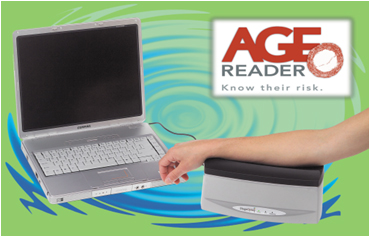
また、本研究室では、健康食品・化粧品素材または製品での抗糖化研究をお考えの企業様向けに、 in Vitroでの抗糖化活性測定を行っております。詳細は以下をご覧ください。
詳細はこちら